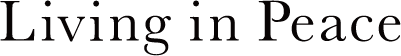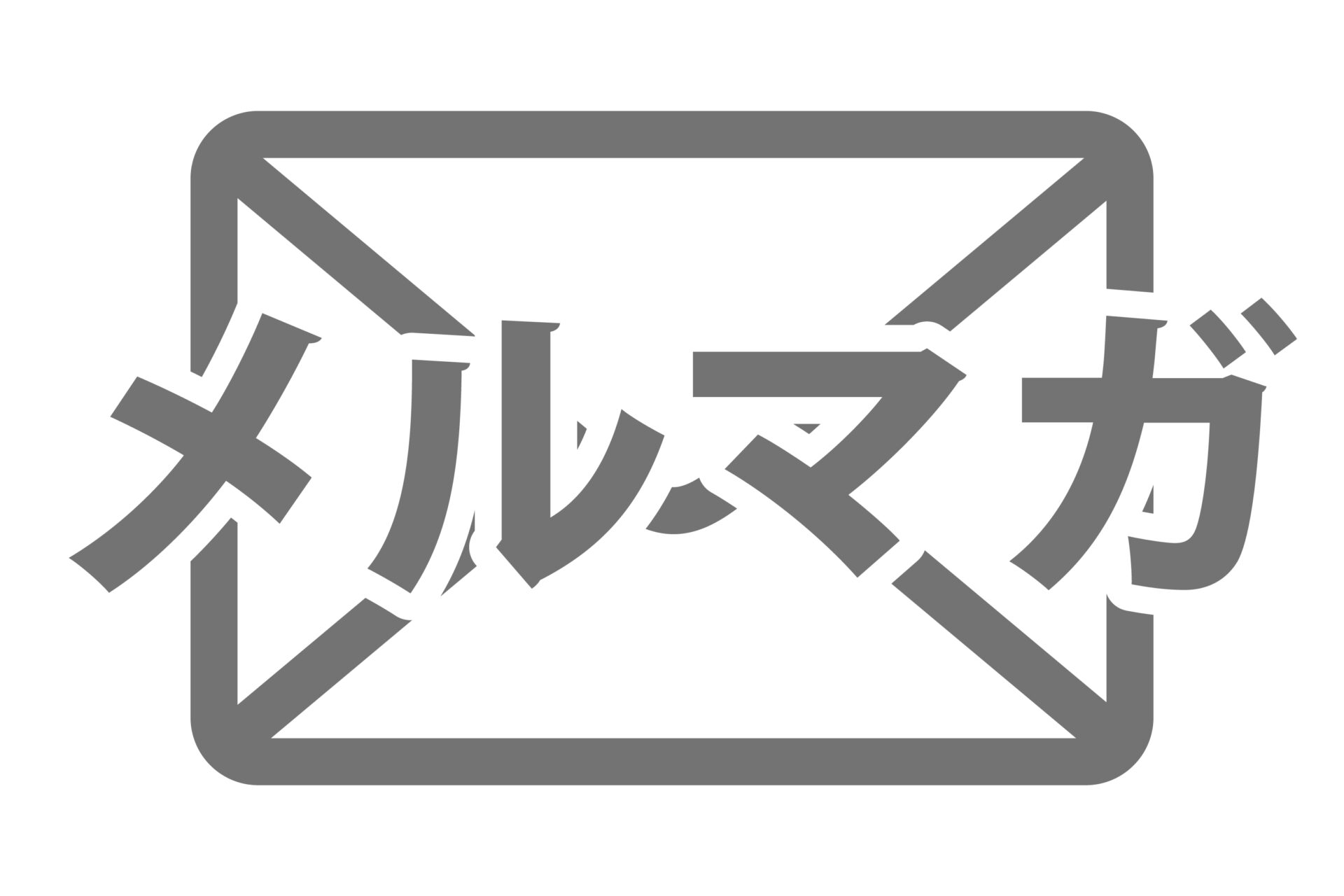Living in Peaceでは、 子どもの体験格差を解消するために、子どもたちに多様な体験・経験を提供する事業として「おでかけリップ」に取り組んでいます。
当初は外国にルーツを持つ子どものみを対象としていましたが、2024年度(24年秋~25年夏)より、母子生活支援施設出身の子どもも対象として事業を行っています。
事業を始めるきっかけとなった、外国にルーツを持つ子どもたちを取り巻く環境や課題、移民・難民困窮家庭への現金給付支援で見えてきた体験格差の実態、これまでの活動内容とプログラム参加者の声についてご紹介します。
外国ルーツの子どもたちを取り巻く環境と課題
日本に住む在留外国人は約320万人(2023年6月末時点)と10年前の約206万人と比べて1.5倍ほど増加しており、家族呼び寄せで来日する子どもや日本で生まれている子どもも増えています。
しかし、移民・難民として来日した人々の多くは低収入です。令和2年に行われた厚生労働省の調査によると、日本人の賃金は月額274,400円(年齢階級30~34歳)ですが、外国人労働者の賃金は月額218,100円(平均年齢33.3歳)と6万円程度の開きがあることが分かっています。
外国人労働者の家庭に育つ外国ルーツの子どもへの支援も少なく、親の経済的困窮や地域社会からの孤立により、子どもの将来の可能性を広げるような、学校や家庭外での体験をさせられていないのが現状です。
さらに、外国ルーツの子どもには言語の壁もありますが、日本語指導が必要な児童生徒数が増えているにもかかわらず、指導者は不足したままであり、学習機会が限定的になってしまうという課題もあります。
移民・難民困窮家庭に対する現金給付支援で見えてきた体験格差の実態
Living in Peaceでは、2021年に複数の都府県で緊急事態宣言が発令されたことを受け、移民・難民として日本で生活する子育て世帯への現金給付支援「移民・難民の子どものいのちを守る基金」を行いました。
支援を受けた方々にヒアリングを行った結果、コロナ禍の解雇等の原因により子どもの学費を払えない、学用品を買えないといった課題の他に、外国ルーツの子どもたちは、他の子どもと比べて、非日常的な体験をする機会に恵まれていないことが分かりました。
背景として、親の経済的困窮や仕事が忙しく時間が取れないこと、さらに親が日本語を苦手としており積極的に子どもと外出できない、子どもが親の代わりに行政手続き等を行っており(いわゆるヤングケアラーの状態)、外出する余裕がないといった現状があります。
外国ルーツの子どもたちは、来日後、親と遠出(おでかけ)をした経験がほとんどない場合もあり、子どもの成長に欠かせない学校外での体験に格差が生じていることが明らかになりました。
令和2年に行われた文部科学省による調査では、小学生の頃に行った体験活動(自然体験・社会体験・文化的体験)の経験は、長期間経過しても、その後の成長に良い影響を与えていることが分かっています。
さらに、収入の水準が相対的に低い家庭の子どもであっても、例えば、自然体験の機会に恵まれていると、家庭の経済状況などに左右されることなく、その後の成長に良い影響がみられるという報告もされています。
全ての子どもたちが様々な体験にチャレンジできる環境作りが大切であり、子どもによって体験機会を得られるかどうかに格差が生じている、いわゆる「体験格差」の問題が社会課題として認知されてきています。
子どもの体験プログラム「おでかけリップ」
そこで、私たちLiving in Peaceは、外国ルーツの子どもたちに、多様な学びや体験の機会を提供するトライアル事業「おでかけリップ」を企画・実施し始めました。
トライアルでは、日本語学習の機会や地域社会とのつながりを持ちづらい外国ルーツの子どもたちに、「おでかけ」を通じて「自分の将来について考えるきっかけ」を提供しています。
主に小学生の子どもと親を対象として、アウトドア活動やテーマパークでの職業体験、古民家での宿泊、農園での野菜の収穫など、学校外での非日常的な体験ができるプログラムにしています。
将来の夢は、幼少期の経験に基づいて気づくことがあるため、「おでかけ」の体験により、子どもたちが将来の可能性を広げ、自分の将来について考えるきっかけ作りになることを期待しています。
また、似た境遇の子ども同士が繋がることで、仲間と悩みや楽しみを共有し、家庭やコミュニティ以外の繋がりを持って成長していけることも期待しています。
各プログラムの最後には、子どもたちに日本語で日記を書いてもらい、当日の振り返りを促しています。日記を書くことにより、日本語能力の向上や、自己表現の機会につなげています。
これまでの活動
2022年度からプログラムの提供を開始し、難民として来日した4家族(年長~小学6年生の子どもとその親。計4カ国。)を対象として全4回のプログラムを実施しました。
- 第1回:東京都秋川渓谷自然人村にてキャンプ
- 第2回:地域でのフィールドワーク(子どもたちが自分で計画)
- 第3回:キッザニアにて職業体験
- 第4回:自分の未来について考えるワークショップ
2023年度には、7家族(小学1年生~中学1年生の子どもとその親。計5カ国。)を対象としてプログラムを実施しました。
- 第1回:千葉県「蓮葉果紅」にてお泊りキャンプ
- 第2回:東京地球農園にて農業体験
- 第3回:都内の会議室にて大学生と年末パーティー
- 第4回:キッザニアにて職業体験
- 第5回:JAXA筑波宇宙センターの見学
- 第6回:岐阜県の国登録有形文化財の住宅にお泊り
- 第7回:そなエリア東京の見学と1年間の振り返り



2024年度より、外国にルーツを持つ子どもだけでなく、学校外での体験が少ない傾向にある母子生活支援施設出身の子どもも対象としてプログラムを開催しました。
外国にルーツを持つ4家族(小学5年生~中学2年生の子ども。)と母子生活支援施設出身の3家族(小学校6年生~中学校2年生とその親。)を対象としてプログラムを実施しました。
※一部の回には対象の子どもの兄弟や親も参加しました。
- 第1回:横瀬町で自然体験~人類の生活に使われてきた石の不思議~
- 第2回:小田原プチ旅行~かまぼこ・ちくわの手作り体験と小田原城の見学~
- 第3回:アイスショーの見学と公演を支える方々へのインタビュー
- 第4回:大阪旅行~国立民族学博物館の見学と関西万博の訪問
- 第5回:日本科学未来館の見学とワークショップ



プログラム参加者の声
参加した子どもたちやその親からは下記のような声をいただいています。
子どもからの声
・でかけるのが好きになった。
・おでかけが好きじゃなかったけど、参加して好きになった。
・一番楽しかったのは、はじめてしんかんせんにのってたのしかったです!
・みんなと仲良くなれて最高だった。
・いい場所に行けて良かった。
・これまで県外に出かける機会がなかったが、いろいろなことが体験できた。
・こんなたいけんができてよかったです。ごはんやバーベキューがとてもおいしかったです。
・おとまりがたのしかった。
・色んな人としゃべれるようになった。
・日本のいろいろな場所や、歴史に興味を持った。
親御さんからの声
・おでかけ企画には、とても感謝しています。
・こどもは楽しんでいたし、ゴールに向かって思考することができていると感じた。
・みんなが「自分のやりたいこと」を考えることができていた。
・「おでかけリップ」をきっかけに、こどもと色んな場所に出かけられるようになった。
・子供は元々デザインが好きだったが、キッザニアでの体験を通してデザインへの関心が一層高まったようだ。
・他の家族と交流できるところがいい。
・将来に向けて意識が出てきたように思います。
・色々な国のお友達と交流が出来た事は娘にとって貴重な経験でした。
今後はプログラムを通じて再認識した子どもたちが抱える課題について、外部団体とも連携しながら、継続的な支援を検討していきます。皆様には温かく見守っていただき、ご支援賜れますと幸いです。
Living in Peaceでは、おでかけリップを運営するメンバーを募集しています。活動にご興味をお持ちいただけましたら、こちらのページよりご応募ください!
活動の概要は以下のスライドもご参照ください。